『世界ウルルン滞在記』というテレビ番組をかつてよく見ました。日本の若い俳優たちが世界各地に行き、そこで暮らす人々と生活を共にする様子を撮ったもので、「心は捨ててしまったら拾えない」とか、「どんなに貧しくても、心が貧しくなってはだめだよ」というような言葉が、ふと現地の人から発せられて、心をうたれる番組です。
ある時の番組では、茸栽培をしている農家の主人が「人が成長を学ぶ学校はない。みんな生活の積み重ねの中から学ぶのだ」と悩みを持つ日本の女優を励ましていました。
このような、日々の暮らしから生まれた、確かな人格の言わせる言葉は、まさに哲学です。
百年一日のごとく日々の営みを繰り返しながら、謙虚に、まじめに、一日一日を大事にして生きている人々の、暮らしの中から析出されてくる、穏やかで静謐な言葉。けなげでやさしく、人を許容しながら勇気づける言葉。そして、どこかに悲しみの水脈を湛えた言葉。
それは、言葉の持つ力によって、「人間である」ことに向けて、人を慰め、励まし、勇気づけてくれます。
それらは、自分の日曜日の夜の気分を少し変えます。明日は、そんな言葉の力を借りて、少しはやさしくなれるだろうかと。
今、教育改革が言われ、「心の教育」とか「探求」とか、いろいろなキャッチフレーズが声高に叫ばれています。そして、「○○をしよう」「○○であるべきだ」等々、いくつもの「であるべきこと」「ねばならないこと」が、シャワーのように子どもたちに、降り注いでいます。
しかし、この番組を思うと、どんな制度もどんな改革も、すぐに滅びてしまう表層のもののように思われ、
それらが不思議と遠い喧騒のように思えてしまいます。
奢らない暮らしを営みながら、このような言葉を育んでいる人々がいるのだ。このような言葉を一人ひとり
の胸底に胎動させることこそが、教育という営みの全てではないか。そう、思わせられるからです。
井伏鱒二の『駅前旅館』という小説に、「信州では山の中の馬子でも馬を曳きながら、中央公論とか文芸春秋といふやうな雑誌を読んでゐるさうだ」という一節がありました。
小説はそのあと、それなら信州の馬子は、往々にして崖から転落するだろう、いや、そんな心配はない、二宮金次郎も薪を背負って、本を読みながら崖の上を歩いていると続くのですが、自分は、ここのところがとても好きです。
「馬子でも」というような表現に問題はありますが、たとえ、自分の仕事の影響を及ぼす範囲が、どんなに小さく狭いものであったとしても、たとえば、この馬子のように、本を読むことを通して、いつも、自らの生き方を検証しつつ自分の暮らしを考え、世の中のあるべき姿に思いをいたし、そして、世界や未来について思いを馳せる。
これこそは、長野県の教育がずっと大事にしてきた「学び」の典型です。
ここには、教育が、なによりも自分で自分が行う「自己教育」であること、そして、教育というものは、生涯にわたって日々の暮らしの中で実践されるものであることが、はっきりと示唆されています。
「子どもが中心」「探求」「生きる力」等々、そんな口当たりのいい上っ面の言葉はもう結構です。子どもたちをせかせか、せかせるのではなく、もっと落ちついて、もつと穏やかに、教育の不易について語りたいものです。
老いの繰り言 2022.8





























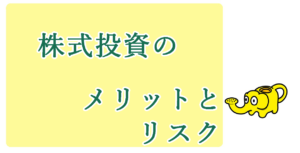
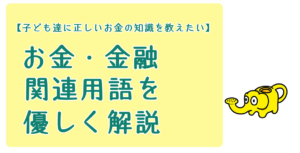
コメント