「落ちて来たら 今度は もっと高く もっともっと高く 何度でも打ち上げよう」
この半年、世界中の人たちは、暗い、やりきれない思いにさいなまれてきたと思う。ロシアのウクライ
ナ侵攻である。
日本では、これに、異常な天気、新型コロナの第7波の急激な拡大が重なり、加えて安倍元総理の銃撃事件や関連する元統一教会問題などがあって、世情騒然として落ち着かず、人々は、途方もない無力感に襲われているようにさえ感じられる。
「何でもありだ」「何でも許されてしまう時代だ」
宮内勝典の、世紀末アメリカの正気と狂気を訪ね歩いた異色のルポルタージュ『宇宙的ナンセンスの時代』を思い出す。
宮内は「テクノロジーの最前線から、砂漠のインディアンや、ニューヨークの裏町にいたるまで」を精力的に駆けぬけて、現代の科学テクノロジーは、それが獲得した巨大な破壊力によって、まさに人類破滅の危機を招いていると観察する。そしてこのパラドックスを「宇宙的ナンセンスの時代」だと断じていた。中岡哲郎も、エネルギーの使用量の増大をとどめることのできない現代の文明は、「全体としては社会そのものが爆発物の上に乗っているような」ものだと指摘していた。
チェルノブイリや福島の原発事故、世界各地の異常気候はこれらの言葉の正しさを、いみじくも証してしまったが、今また、世界は、ウクライナの戦争を目の当たりにして、自らの影に怯えている。
フランツ・ファノンは言っていた。
ひとつの橋の建設がもしそこに働く人々の意識を豊かにしないものならば、橋は建設されぬがよい。市民は従前どおり、泳ぐか渡し船に乗るかして川を渡ればよい。 (『地に呪われたる者』)
思えば、人間は「ファノンの橋」からなんと遠いところに来てしまったことか。人類を絶滅できる科学
テクノロジーが全世界を覆い、そしてそのような科学を支える思想や常識や感覚にびっしりと塗りこめられて、自分たちの暮らしもある。
とすれば自分たちもまた、宮内が会ったニューヨークの若者たちのように、自虐と、その裏返しである苛虐の中で、深い孤独を育みつつ生き続けなければならないのだろうか。
だが、「いや、違う」と、心の底で、声がする。
ひとつの言葉に励まされて生きるということが、人間にはある。ひとつのフレイズによって慰められ、ひとつの文章に勇気づけられて生きるということが、人間にはある。いや、正確に言えば、動物の中で、ひとつの言葉に支えられて生きることを選択したものが人間ではなかったか。
そして、そのような言葉のひとつとして、たとえば、黒田三郎の「紙風船」という詩が、かつて自分にもあったのではなかったか。
落ちて来たら
今度は
もっと高く
もっともっと高く
何度でも打ち上げよう
美しい
願いごとのように
この詩は、紙風船を歌いながら、より多く人間の「美しい願いごと」を歌っている。紙風船に働く力は、落下という物理的な法則に基づくもののほうが、もちろん強い。にもかかわらず、それに抗して人間は何度でも何度でも紙風船をうちあげようとするのである。それこそが人間的な営みというものではないか、それこそが、美しい願いごとを求めて生きようとする人間の、人間たるゆえんではないのか。
こうして、青空にくり返しうちあげられる紙風船のイメージは、時に落ち込もうとする自分の青春の一時期の揚力となってくれたのだ。
だから、「にもかかわらず」と「一寸の虫」は思わなければいけないと、思う。
世界を覆う暗闇の巨大さが、たとえ一人の、ちっぽけな人間の生き方などを、虫けらのように蹴散らすとしても、かつて出合った言葉たちは、我々に、「宇宙的ナンセンスの時代」の重力圏から脱出したいと意志し、時代とは逆のヴエクトルを進めと使嗾してくる。
だから、巨大でいかんともしがたい「限りない愚かさ」(中島みゆき)の渦中にいるからこそ、どんなに小さくどんなに短くても、「ファノンの橋」を架けなければならない。
そのようにして、言葉は、微小な存在を辛うじて充填し、輝かせ重くするのだ。
老いの繰り言 7月





























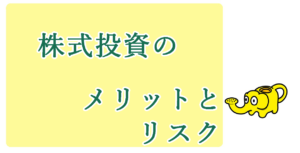
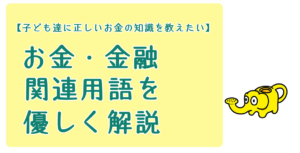
コメント